守貞漫稿(もりさだまんこう)は1838年(天保9年)に喜多川守貞によって起稿され、1853年(嘉永6年)に一度完成し、1867年(慶応3年)に加筆され、約30年間で全35巻書かれました。しかし、刊行されることはなく、1908年(明治41年)に帝国図書館の所蔵となっていた稿本を整理編集して『類聚近世風俗志』として出版されたものです。この書物には『醴賣り』という記述の甘酒に関係のあるキーワードが出てきます。
守貞漫稿が書かれた頃の時代背景と江戸の甘酒売り
守貞漫稿が起稿された頃は、医学では蘭学が発展し、海外船も日本に沢山来るようになっていた時期で、幕藩体制もうまくいかなくなっていた頃でした。書が完成した翌年1854年は、かの黒船で有名なアメリカのペリー提督が幕府に開国させた年で、1867年は幕府が終わり迎えた大政奉還の年であり、幕末から明治の境という時代の変革期に作られた本書はまさに江戸末期の日本の文化(食文化)を知るのに非常に面白いものであると思います。
本書の内容は主に江戸と関西(京都・大阪)という、日本の中心地となった歴史ある都市間の文化の違いを比べて詳しく書かれています。この守貞漫稿6巻23頁、類聚近世風俗志第5編の生業下164頁に江戸や京都・大阪の『甘酒売り』に関する記載があります。
本文より訳すと、
甘酒売り
夏月に専ら売り巡る者は醴(あまざけ)売りなり。京坂(京都・大阪)は専ら夏夜のみこれを売り、一碗を六文(120~180円)とした。江戸は四時にこれを売り、一碗を八文(160~240円)とした。蓋(ふた)は似ているけど、釜は江戸では真鍮製や鉄製を用い、鉄製の物は、京坂と同じく宮中にあり、京坂では必ず鉄製を用いる為、釜は皆宮中にある。小川顕道(1737~1816年)が記した塵塚談(1814年)には、『30歳の頃(1767年)までは寒い冬の夜のみ売り巡っていた。しかし、今は暑中往来を売り、夜に売っているものは少ない。浅草本願寺前の甘酒店は古く四季を通して売っている。四季通して外で売っている所は江戸中で45軒ある。』とある。
※塵塚談…1814年(文化11年)に小川顕道が著(あらわ)した随筆集。
この様に、1838年以降の江戸や関西では主に夏に甘酒が売られており、四季を通しても売られるようになっていたことが読み取れます。また塵塚談からは、小川顕道が30歳であった1767年頃は、寒い冬の夜だけ売られていたが、1814年までには夏に売られるようになったこともわかります。
つまり、1767~1814年間に掛けて甘酒が夏に飲まれるように推移していったことがわかり、何に起因しているのか気になる所です。
※類聚近世風俗志第5編生業下164頁より引用
甘酒売りの挿絵を見ると、江戸の甘酒売りの籠には『もち甘酒』の文字があり、もち米を用いた甘酒を売っていたのだろうと読み取れます。また関西の甘酒売りの籠には甘酒を熱している様子が伺えられ、温かいものを売っていたことがわかります。
また文献にも『醴』と書いて『アマザケ』と宛てており、江戸時代には『醴』が古代のみりん系の甘い酒ではなく、今日の甘酒に近いものであったことが伺えます。
参考文献
・国立国会図書館デジタルコレクション:守貞漫稿6巻23頁
URL:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592395/23
・国立国会図書館デジタルコレクション:類聚近世風俗志第5編生業下164頁(コマ番号104)/挿絵引用
URL:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444386/104
・新もういちど読む山川日本史:山川出版社/五味文彦・鳥海靖 編/219~237頁
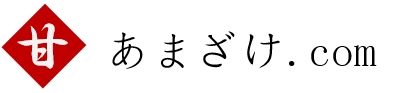

コメントを残す