日本書紀は、681年に天武天皇が川嶋皇子らに撰修を命じ、713年の元明天皇(43代)の勅命により、舎人親王や大安麻侶によって完成され、720年に元正天皇(44代)に撰上された全30巻の歴史書です。この書物には『天甜酒(あまのたむけざけ)』、『醴酒』の記述で甘酒に関係のあるキーワードが出てきます。
日本書紀に書かれた天甜酒と醴酒
日本書紀は神々の時代から697年の持統天皇(41代:天武天皇の皇后)までの歴史が記されています。この書物の第2巻に『天甜酒』が、第10巻に『醴酒』が出てきます。
天甜酒
天甜酒(第2巻・神代下)に関しては、文を挙げると、
神吾田鹿葦津姫、卜定田を以って、狭名田と名付ける。その田の稲を以って、天甜酒を醸みて嘗す。又、淳浪田の稲を用て飯を為ぎて嘗す。
※卜定田(うらへた)…占いによって神の貢ぎ物の田を定める
※狭名田(さなだ)…神に供える稲を作る田。鹿児島県霧島市に『狭名田の長田伝説』というものがあるそうです。長田とは文字通り長い田んぼの意です。
※淳浪田(ぬなた)…水田
とあり、訳すと、木花咲耶姫は天甜酒と飯を造り、献げて新嘗祭(神に秋の収穫の御礼をする祭)をしたという事が謳われています。
甜のタムケは美味飲食を表すともありますが、天甜酒を分けて考えると、『天』は天の・神の意、『甜』は甜菜糖などにも使われている様に甘いの意、神(天)の甘い酒という意味ではなかったのかなと思います。このお酒が、口噛ノ酒(唾液の酵素で糖化)か麹の酒(麹の酵素で糖化)かは、定かではありません。
別説によると、木花咲耶姫がホオリ(山幸彦)を産んだ際に、祝いに父神である大山祇命が造ったなんて話もありますが、どちらが本当なのでしょうか?男性の口噛み酒というのは…でも、まぁ、神様だしな…
この大山祇命(オオヤマツミ)と木花咲耶姫は、酒解神と酒解子神として酒造に関連する神社の主祭神としてよく祀られています。
醴酒
醴酒(第10巻・応神天皇19年(289年頃))に関しては、本文を訳すと、
289年(応神天皇19年)、吉野宮にて、国栖人(くずびと)が来て天皇(応神天皇:15代)に醴酒を献った。
※国栖人…奈良県吉野地方にいた土着の民
とあり、この内容だけだとどのような酒なのかは、わかりません。
しかし、平安時代(927年)の法律書『延喜式』に『醴酒』は一晩で出来る米・米麹・酒で仕込んだみりん系の甘い酒だという事がわかっているので、この書物が作られた奈良時代(720年頃)を考えてもそんなに差はなかったのではないかと思われます。また天皇に献じられる酒であったことからも高級酒(御酒糟)であったことは確実でしょう。
まとめ
この様に、天甜酒の味が定かではありませんが、甜という文字から、甘かったのかな?という予想です。
醴酒は延喜式に記載のある同名の酒より、甘い酒だったのだろうという考えに至りました。
いずれも、現代の甘酒とは違うものであったのはことは確実だろうと思います。
参考文献
・「日本書紀」に現われた酒/加藤百一
・国立国会図書館デジタルコレクション:日本書紀巻2神代下(慶長4年1599年)天甜酒
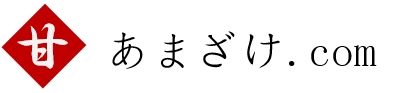
現在の日本酒の一種の貴醸酒がそれに近いと思います。Wikiによると平安時代の古文書『延喜式』(927年)に記されている宮内省造酒司による古代酒の製法「しおり」と近いものとなっている。 (引用終わり)と書いてあります。実際に飲んだことがありますが、結構とろみがあって、あま〜いお酒で、好きです。
龍野さん、コメントありがとうございます!
実は、調べているときにどこかの文献で貴醸酒の記載を見た記憶はありますが、目に留まっていなかったので改めて調べてみました。
たしかに『貴醸酒』は、延喜式の中の『醴酒』というお酒が、酒で仕込むみりん系の酒で近いものになります。
現在の清酒は、酒母造りで事前にアルコール耐性の高い酵母を増やしてから醪造りの工程に移行してアルコール度数20%ほどの原酒を得ます。
奈良時代の酒は、酒母造りの概念がなかったので、一度の仕込みで高いアルコール度数のお酒が得られませんでした。
なので、仕込んでは、絞って酒を得て、その酒を再度仕込みに使っての工程を何度か繰り返して高いアルコール度数のお酒造っていたそうで、これを「しほり法」と言います。
自分もまだ、そのお酒は飲んだことがないので飲んでみたいです♪
ちなみに、みりんも清酒・米・米麹で仕込むものなので、貴醸酒の貯蔵期間が短いものは、みりんの貯蔵期間が短いものと同じ味わいかと思います。貯蔵期間が長くて、琥珀色に変わったものも、たぶん近しい味わいかと思いますので、みりんもチャレンジしてみてください(笑)